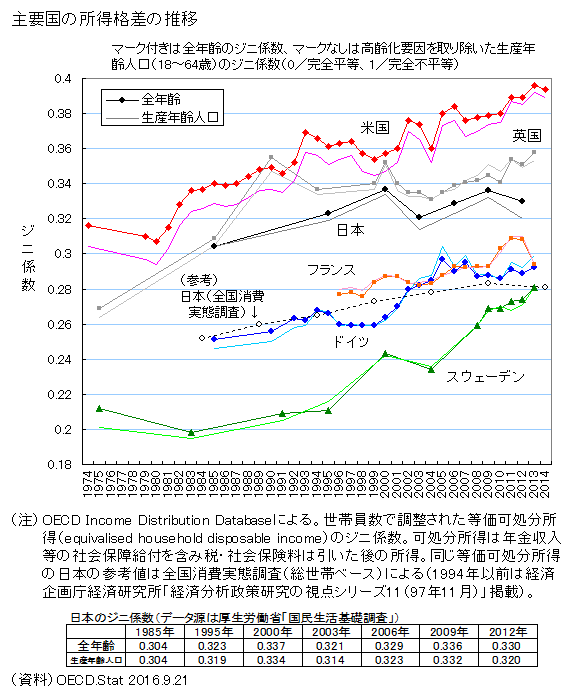国民主権は名のみで権力はこれら管理者たちがほしいままにしている。
これがカレル・ヴァン・ウォルフレン日本論の骨子である。
主なところを敷衍してみよう
戦後の奇跡的な経済発展も「管理者たち」の主導によるものであったがそれは国民生活の犠牲の上に築かれたものでありその結果「富める国の貧しい国民」になった。
政治的には大多数の国民は「知らしむべからず」にされても特段声を大にして抗議しない。
一部を除き大多数の国民は政治について「しかたがない」と思い特段の関心を抱かない。
日本独特の記者クラブ制はこの管理者たちによる「知らしむべからず」政策に寄与してきた。
この制度によってジャーナリストたちの報道の自主制と独立制を損なわれた。
情報は統制され国民は事実を知る機会が制限された。この制度は戦時中のかの悪名高い大本営発表の伝統を受け継ぐもので日本がいまだ民主主義でない証である。
民主主義社会では「管理者たち」は主権者である国民に対し自分たちの行動について「説明責任」を果たさなければならない。
ところが国民が政治に無関心であることを見透かし彼らは「説明責任」を果たさないでやりたい放題である。
特に官僚は自分たちの管轄領域では事実上主権をにぎりあたかも小国家のように振舞っている。
このような官僚の専横がまかり通ったのはアメリカという後ろ盾があったればこそである。
アメリカの後ろ盾が日本の官僚を増長させ政治的説明責任の不在を招いた。
外交も経済もアメリカの庇護のおかげで日本はわずらわしい外交から免除され経済だけに集中することができた。
カレル・ヴァン・ウォルフレンは、日本社会を30年にわたり観察してこのような結論に至った。
何が真実で何が偽りであるか、その内容の豊富さと正確さは驚嘆に値する。
彼の日本社会に対する指摘は綿密な調査とデータにもとずき反駁の余地がないほど的確であるが、いくつか疑問点はある。
第1に、カレル・ヴァン・ウォルフレンは、日本の奇跡的経済発展は中流階級の犠牲のうえに築かれたというがはたしてこれは事実か。
日本人は家庭生活を犠牲にしてまで会社のために尽くすという一面がある。西欧社会ではあり得ないことであろう。
問題はなぜそうするかである。カレル・ヴァン・ウォルフレンは、「管理者たち」が従順な中流階級にそれを強いたからであるという。
だがそれは物事の反面を言い表しているにすぎない。
会社は利益を目的とした機能集団である。一方村落、宗教、血縁などのつながりを基盤とする組織は共同体である。
戦前まで日本社会は主に隣組、氏子、檀家、親戚などの共同体から成り立っていた。もちろん機能集団たる会社はあったが共同体とは全く別に存在していた。
ところが敗戦を機に日本は経済優先から次第に会社を中心とした社会へと変わっていった。このため共同体の存在が希薄になり次第に表向きの社会から消滅していった。
共同体の機能は社会から全くなくなるわけではなく時代の要請からその行く先を会社に求めた。かくて共同体の機能が機能集団である会社に潜り込んだ。
この結果日本の会社は、機能集団と共同体の性格を合わせもつ組織になった。
たとえば会社単位でお祭りや運動会を開催したり、社員の家族に不幸があれば休日返上でみんなが手伝いにいく、などは共同体の特徴でこそあれ利益を目的とした機能集団のそれではない。
このように社員が家庭を犠牲にしてまで会社のために働くのは決して「管理者たち」の強制だけによるものではなく、会社の共同体化によるものでもある。
第2に、カレル・ヴァン・ウォルフレンは、日本を最も深く理解したという著名なカナダ人研究者E・H・ノーマンの日本評の結論(下)を引用してノーマンの考えに賛成している。
「日本の少数の独裁者は、自分たちの最大の資源を理解しなかったーすなわち、日本の人びとを。
明治の独裁者たちは、社会的階層の低位にいる同胞たちに冷淡だった。
彼らは人びとを酷使し、残忍に扱った。兵士にする以外に価値はないと思い、生産マシーンのもの言わぬ歯車として使うことしか考えなかった。
明治の少数の独裁者の第一世代は、普通の人びとの偉大な可能性を見誤ったのだ。
彼らは、日本を近代国家に転換させるという大事業にとりかかったときでさえ、人びとを偉大で自由な国家に貢献する有能な人びとだとは見なさなかった。」
(カレル・ヴァン・ウォルフレン著鈴木主税訳新潮文庫『人間を幸福にしない日本というシステム』)
カレル・ヴァン・ウォルフレンは、この明治維新の経緯から「管理者たち」が国民を歯車の一部と考えて日本の非公式の権力システムをほしいままにしている原因であるという。
下級武士出身の革命家たちが当時の国民をもの言わぬ歯車と考えていたというがそれは説得力に欠ける。
福澤諭吉の『学問のすすめ』が300万部も売れたという。当時の人口から推定して0歳児を含めた全国民の10人に1人が読んだことになる。驚嘆すべき数字である。
国民の教育レベルとモチベーションの高さが当時の社会には既に存在していた。このような国民がもの言わぬ歯車であるはずがない。
第3に、社会変革期の特殊事情がある。
20世紀オーストリアの心理学者ジークムント・フロイトは幼児期体験の決定的重要性を強調した。
幼児期の経験は人格形成に影響しその後の人生に影響し続けるという。
国家もまた然り。たとえばアメリカは独立戦争の前後に多くの偉人を輩出し彼らの言行がその後のアメリカ国民の慣行を規定した。 イギリス革命やフランス革命にも同じような事がいえる。
韓国の独立は自ら勝ち取ったのではなく日本がアメリカに敗れたことによりもたらされた。この独立の経緯がいまなお韓国の対日感情を束縛している。
日本は既存体制の綻びと外国の脅威もあり自らの力で明治維新を成功させた。
この革命を主導したのは一部の下級武士である。
この事実は重要である。革命を主導した下級武士がその後支配者として君臨したからである。
近代日本夜明けのこの幼児期体験がその後の日本の行動を規定した。
この革命で国民の大半は傍観者か付和雷同者にすぎなかったが教育のレベルは高かった。
社会が変革する時にはあたかもその時を待っていたかのようにどこからともなく英雄・偉人が雲霞のごとく現れてくる。
彼らは社会的階層の低位にいる物言わぬ人たちの代弁者であってそれらの人たちを蔑んだり物扱いしているわけではない。社会が変革する時にはあたかもその時を待っていたかのようにどこからともなく英雄・偉人が雲霞のごとく現れてくる。
明治維新後に支配者となった下級武士たちとて例外ではない。
カレル・ヴァン・ウォルフレンは日本評の最後に "最も書きづらい” と前置きしながら日本に対して提言している。その提言につき考えてみたい。