戦後日本の急性アノミーの原因として、前稿では、わが国の受験戦争と自虐史観教育をあげた。このほか急性アノミーの原因として共同体の崩壊は深刻である。
順次、敷衍したい。
まず、受験戦争から。
教育の本来の目的は、人間らしい人間を作ることである。幕末、長州の吉田松陰は、松下村塾記に、「学ぶとは人たる所以を学ぶことなり」 と塾の基本方針に掲げている。
ところが戦後の教育を俯瞰するに、これら理念とは程遠い教育がなされ、ついには受験戦争と呼ばれるまでに至った。特に1979年(昭和54年)1月の共通一時試験導入からその傾向は顕著になった。
何故にこのようになったのか、淵源は明治初期の官僚育成のための学校創設に遡る。明治政府は官僚育成学校として、東京帝国大学法学部を創設した。
日本をいち早く西欧の近代国家に並ぶべく、官僚機構を最大限活用し、見事その目的を達成した。この官僚機構は、敗戦で一度挫折はしたものの、米軍の占領政策上の都合でたちまち蘇り、戦後の高度成長にも貢献した。
ところが発展途上であった日本にとって有効に働いたこの官僚機構であったが、成熟した日本にとっては徐々にその弊害が目立ち始めた。
試験を通じて選ばれた特権階級はその権力を恣にした。これを見た日本中の若者がそれを目指すようになった。
勿論、これは象徴的な出来事であるが、この現象は、官民問わずわが国のあらゆる分野に影響を及ぼした。
受験戦争の勃発である。
受験戦争は、受験生を無理やり相対評価によって振り分け、教材あるいは試験を全国一律にすればする程競争意識がいやがうえにも高まった。
成熟しつつあった日本で、試験を多様化すべき時に、導入された共通一次試験は受験戦争回避の歯車を完全に逆回転させた。
かくして受験戦争の犠牲になり相対評価で強制的に差別させられる若者の間から、徐々に連帯の意識は薄れ、同世代の仲間を敵とみるようになった。
因みに、一定のレベルに達すれば可とする、運転免許試験のような絶対評価試験では受験戦争は起こり得ないし、電気技士試験を受ける若者とボイラー技士試験を受ける若者とのあいだには何の競争も生まれない。
夫々が他と比較されることなく、独自に自分の目指す道に邁進するだけであり、及第しなければ、さらに自分を磨いて精進するだけである。
そこではけして他人を競争相手と見ることもない。
受験戦争回避のキーワードは、絶対評価と多様化。
成熟した日本社会には、受験戦争は若者間の連帯感を引き裂くという害こそあれいかなる利点も見出せない。
遡って、爾後の成果をみるかぎり、明治政府の官僚育成政策に異論を差し挟む余地はない。
問題とすべきは、この政策が時代を経るにしたがって制度疲労を起こしたにも拘わらず、一向に是正されなかったことである。
日本は、古来、中国や朝鮮半島からさまざまな多くのものを受け入れてきたが、例外的にどうしても受け入れなかったものがある。
宦官、纏足および科挙である。中国史家によれば、いまわしい食人の習慣もこれに加わる。
このうち科挙制度は、一時、奈良時代に入ったが定着しなかったという記録がある。
が、今日、官僚の日本社会における壟断ぶりをみると、奈良時代に一時的に入り、すぐに廃れたはずの科挙制度が復活したのではないかと思わせるものがある。
日本人は本来このような制度には馴染まない筈である。それが証拠に、科挙制度を受け入れる機会はいくらでもあったが、現在まで受け入れてこなかったという厳然たる歴史的事実がある。
現代の日本社会において、これ以上、官僚の壟断を許せば、それは紛れもなく中国の科挙制度時代と同じく官僚壟断社会の再現となる。中国の科挙制度がもたらす官僚の腐敗・腐蝕は言うを俟たない。
官僚の力の源泉は、相対評価試験によってもたらされた。この相対評価試験制度を改たむるに、官僚に任せるほどあてにならないことはない。
この改革は官僚機構と無縁のところからなされるだろう。
が、その時期はいつなのか、またそれを成し遂げるのは誰なのか、予測さえできない。
日本社会から、受験戦争を追放すること、そして若者の間の連帯感を呼び覚ますこと、いずれも喫緊の課題である。
2013年7月29日月曜日
2013年7月22日月曜日
アノミー 1
社会の規範が崩壊することによる無規範状態、アノミーが原因と思われる事件が後を絶たない。
最近、この種悲劇的な事件が2件も起きた。
長崎市の市立小学校6年の女子児童の自殺未遂事件と、広島・呉市の16歳女子殺害事件である。
前者は、修学旅行の班決めで同じ班になった同級生の1人が他の3人に仲間外れにしようと呼びかけたが、3人は同意せず担任に相談した。
同級生は謝罪したが、女子児童は2日後に自殺を図った。女子児童にとっては、最も楽しかるべき心弾む修学旅行をまえに、仲間外れにされようとしたこと自体、耐え難い苦痛であったのだろう。察するに余りある。せめてもの救いは、3人がいじめに同意しなかったことであろうか。
後者は、同じ16歳の女子が互いに仲違いし、一方が殺害されるという荒んだ痛ましい事件であった。
この事件で注目すべきは、被害者・加害者双方ともに面識もない同じ16歳の2人の少女が加害者として凶行に加わっていることである。
この2つの事件に共通していることは、いじめ、もしくは凶行に加わった主体が、一人ではなく複数人で係わろうとしたことであり、被害者は一人であるが、この被害者は、状況によってはいつでも他と換わりうることである。
このことは、その場の空気によって誰でも簡単に加害者にもなり被害者にもなり得ることを示している。
だれかが、いじめ、もしくは凶行の空気をつくろうすると、もちかけられた関係のない人もその空気に逆らえない。さもないと自分が被害者になりかねないから。
かくして救いようのない事件が後を絶たない。
犯罪はいつの時代でもおこるし、犯罪者が絶えることもない。
が、忌み恐るべき事は普通の人間がいとも簡単に犯罪に巻き込まれる可能性があることを上記の事件は示していることである。
何か得体のしれない ”空気”により醸成された犯罪に。
空気による犯罪に巻き込まれる原因は、社会における無連帯、無規範である。特に若者の間の連帯がズタズタに引き裂かれていることに起因している。
敗戦後わが国を襲った急性アノミーは、未だ亡霊のごとく付きまとって離れないでいる。
特に、戦後教育でなされた、自虐史観教育と受験戦争は急性アノミーを一段と助長した。
自虐史観教育は、自国に対する誇りを奪う教育であり、最近とみに、中韓両国からこれを逆手にとった発言が目立ち、ややもするとわが国において自虐史観教育が拡大再生産されかねない危険な情勢になっている。
自国に誇りをもてない国民の間にどうして連帯感が生まれようか。
受験戦争は、同世代の仲間をすべて敵と見立てる教育システムに外ならない。これでは、若者の間に連帯感が育ちようがない。
こういうとすぐ受験戦争は、いつの時代でもあったではないかという反論がくる。
たしかにあったかもしれないが、戦後の受験戦争のように教育の本来の目的から外れることはかってなかった。
しからば、教育の本来の目的とは何か。
答え、人間らしい人間を作ることである。
機械のような画一人間を作ることが教育の本来の目的である筈がない。
独裁国家ではあるいはそういう教育がなされるかもしれないが、それは教育ではなく洗脳と言うべきだろう。
すくなくとも、現在の画一式の○X試験、受験年齢の低学年化などとは縁遠いものであった。数多くの受験生から、単純に反射神経に優れているものだけを機械的に選りすぐる受験戦争ではなかった。
連帯なき社会は、病める社会であり、混迷し、やがて犯罪の温床と化す。そこでは、ごく普通の人間が信じられないような行動をする。
凶悪事件を起こした犯人について、日ごろ犯人をよく知っている人の感想を新聞やテレビでときどきみかける。曰く
「ごく普通の礼儀ただしい、おとなしい、いい人でした。あんな事件を起こすなんて今でも信じられない」 と。
無規範、アノミーが人を狂気にするなによりの証左がこの感想にこめられている。
最近、この種悲劇的な事件が2件も起きた。
長崎市の市立小学校6年の女子児童の自殺未遂事件と、広島・呉市の16歳女子殺害事件である。
前者は、修学旅行の班決めで同じ班になった同級生の1人が他の3人に仲間外れにしようと呼びかけたが、3人は同意せず担任に相談した。
同級生は謝罪したが、女子児童は2日後に自殺を図った。女子児童にとっては、最も楽しかるべき心弾む修学旅行をまえに、仲間外れにされようとしたこと自体、耐え難い苦痛であったのだろう。察するに余りある。せめてもの救いは、3人がいじめに同意しなかったことであろうか。
後者は、同じ16歳の女子が互いに仲違いし、一方が殺害されるという荒んだ痛ましい事件であった。
この事件で注目すべきは、被害者・加害者双方ともに面識もない同じ16歳の2人の少女が加害者として凶行に加わっていることである。
この2つの事件に共通していることは、いじめ、もしくは凶行に加わった主体が、一人ではなく複数人で係わろうとしたことであり、被害者は一人であるが、この被害者は、状況によってはいつでも他と換わりうることである。
このことは、その場の空気によって誰でも簡単に加害者にもなり被害者にもなり得ることを示している。
だれかが、いじめ、もしくは凶行の空気をつくろうすると、もちかけられた関係のない人もその空気に逆らえない。さもないと自分が被害者になりかねないから。
かくして救いようのない事件が後を絶たない。
犯罪はいつの時代でもおこるし、犯罪者が絶えることもない。
が、忌み恐るべき事は普通の人間がいとも簡単に犯罪に巻き込まれる可能性があることを上記の事件は示していることである。
何か得体のしれない ”空気”により醸成された犯罪に。
空気による犯罪に巻き込まれる原因は、社会における無連帯、無規範である。特に若者の間の連帯がズタズタに引き裂かれていることに起因している。
敗戦後わが国を襲った急性アノミーは、未だ亡霊のごとく付きまとって離れないでいる。
特に、戦後教育でなされた、自虐史観教育と受験戦争は急性アノミーを一段と助長した。
自虐史観教育は、自国に対する誇りを奪う教育であり、最近とみに、中韓両国からこれを逆手にとった発言が目立ち、ややもするとわが国において自虐史観教育が拡大再生産されかねない危険な情勢になっている。
自国に誇りをもてない国民の間にどうして連帯感が生まれようか。
受験戦争は、同世代の仲間をすべて敵と見立てる教育システムに外ならない。これでは、若者の間に連帯感が育ちようがない。
こういうとすぐ受験戦争は、いつの時代でもあったではないかという反論がくる。
たしかにあったかもしれないが、戦後の受験戦争のように教育の本来の目的から外れることはかってなかった。
しからば、教育の本来の目的とは何か。
答え、人間らしい人間を作ることである。
機械のような画一人間を作ることが教育の本来の目的である筈がない。
独裁国家ではあるいはそういう教育がなされるかもしれないが、それは教育ではなく洗脳と言うべきだろう。
すくなくとも、現在の画一式の○X試験、受験年齢の低学年化などとは縁遠いものであった。数多くの受験生から、単純に反射神経に優れているものだけを機械的に選りすぐる受験戦争ではなかった。
連帯なき社会は、病める社会であり、混迷し、やがて犯罪の温床と化す。そこでは、ごく普通の人間が信じられないような行動をする。
凶悪事件を起こした犯人について、日ごろ犯人をよく知っている人の感想を新聞やテレビでときどきみかける。曰く
「ごく普通の礼儀ただしい、おとなしい、いい人でした。あんな事件を起こすなんて今でも信じられない」 と。
無規範、アノミーが人を狂気にするなによりの証左がこの感想にこめられている。
2013年7月15日月曜日
労働と気晴らし
17世紀フランスの天才ブレーズ・パスカルは、人間の尊厳は、なにより考えることにあり ”人間は考える葦である” といった。
彼の興味は数学や物理学にあり、この分野で目覚しい業績を残したが父の死を契機としてその鋭い観察眼は人間に向けられた。
彼が著した、パンセのなかで特に興味を惹くのは、人間の行動を観察した次の3点であろうか。
① 人間はいずれ避けられない死の恐怖におびえている。
② 人間の行動は、全て自己愛からきている。
③ 苦悩や不幸から逃れるための”気晴らし”は、その瞬間だけ人間を幸福にする。
① 人間はいずれ避けられない死の恐怖におびえている。
② 人間の行動は、全て自己愛からきている。
③ 苦悩や不幸から逃れるための”気晴らし”は、その瞬間だけ人間を幸福にする。
① と ② は、必然的に、関心が宗教の世界に向かい、彼独特のキリスト教弁証論を展開した。
宗教、特にキリスト教は、西洋文明を理解するには避けて通れないが、ここでは、 ③ の”気晴らし”について考えてみたい。
われわれは、身近な人の死やその他不幸のどん底にあると自らも思い、傍からもそう思われている人が、時も経ぬ間に、その不幸を忘れたかのように振舞うのをしばしば見かける。
パスカルは看破する。人間は深刻なことに向き合えるほど強くない。なにもしないでいることほど人間にとって過酷なことはない。したがって、人間は気晴らしを求め、その瞬間は人間を幸福にする、と。
パスカルの思想には、キリスト教ジャンセニスム教説が色濃くあらわれているといわれる。
これと関連して、ドイツの社会学者マックス・ウエーバは、彼の論文 「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」に、キリスト教カルヴァン派が、近代資本主義の精神に少なからず影響を及ぼしていると述べている。
パスカルは人間は”気晴らし”によってつかの間の幸福を得ることができるといい、マックス・ウエーバは、彼の論文で ”労働は救済である” と述べ ”祈りかつ働く” ことが宗教的救済につながるとの説を展開している。
両者に共通しているのは、無為、または、祈り、だけでは、幸福になれないし、救済もされないということになる。
さらにもっと重要な共通点は、ジャンセニスム教説もカルヴァン派も、人間の運命は予め定められているという、予定説から成立っていることである。
予定説は、救済される人間は予め決定されている。
善いことをしたから救われるとか悪いことをしたから救われないとか人間の都合に左右されない、神の絶対性を守るための教義である。
善行を働いても救われないかもしれないし、悪行を働いても救われるかもしれない。しかも人間はこのことを予め知ることさえできない。
この予定説の論理は、人間を不安にする。この不安から逃れるため、もし自分が、神によって救われている人間ならば、神の御心に従う行動をとる筈だと、贅沢や浪費を避け、禁欲的労働に勤しんだ。
そして ”祈りかつ働く” ことによって社会に貢献し、神の御心に適うことによって、はじめて自分が救われているという確信をもつことができる。
仏教でいう因果応報の逆で、自分が既に救われているのであれば、それに相応しい行動をとっている筈である、という緊張感あふれる精神状態を強いている。
凡俗の発想かもしれないが、マックス・ウエーバが、”労働は救済である” といっても、労働が苦痛を伴うものだけのものであれば、これほどまでに、近代資本主義は伝播しなかったであろうと思われる。
パスカルが、看破したように、人間は ”気晴らし” を求めているが、労働もその要素をあわせ持っていたからこそ、今日の近代資本主義の隆盛を迎えたといえないだろうか。
因みに、今日のヨーロッパにおける経済状況は、プロテスタントが占める割合が比較的多い北欧の経済が順調で、プロテスタントが占める割合が少ない南欧の経済は危機に瀕している。
これは、マックス・ウエーバがいう、プロテスタンティズムの倫理が比較的浸透している北欧諸国とそうでない南欧諸国の差によって生じているかもしれない。
もしそうであれば、欧州の南北の経済格差は一過性のものではないということになる。
EUの経済格差問題は思いのほか根が深い。
これと関連して、ドイツの社会学者マックス・ウエーバは、彼の論文 「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」に、キリスト教カルヴァン派が、近代資本主義の精神に少なからず影響を及ぼしていると述べている。
パスカルは人間は”気晴らし”によってつかの間の幸福を得ることができるといい、マックス・ウエーバは、彼の論文で ”労働は救済である” と述べ ”祈りかつ働く” ことが宗教的救済につながるとの説を展開している。
両者に共通しているのは、無為、または、祈り、だけでは、幸福になれないし、救済もされないということになる。
さらにもっと重要な共通点は、ジャンセニスム教説もカルヴァン派も、人間の運命は予め定められているという、予定説から成立っていることである。
予定説は、救済される人間は予め決定されている。
善いことをしたから救われるとか悪いことをしたから救われないとか人間の都合に左右されない、神の絶対性を守るための教義である。
善行を働いても救われないかもしれないし、悪行を働いても救われるかもしれない。しかも人間はこのことを予め知ることさえできない。
この予定説の論理は、人間を不安にする。この不安から逃れるため、もし自分が、神によって救われている人間ならば、神の御心に従う行動をとる筈だと、贅沢や浪費を避け、禁欲的労働に勤しんだ。
そして ”祈りかつ働く” ことによって社会に貢献し、神の御心に適うことによって、はじめて自分が救われているという確信をもつことができる。
仏教でいう因果応報の逆で、自分が既に救われているのであれば、それに相応しい行動をとっている筈である、という緊張感あふれる精神状態を強いている。
凡俗の発想かもしれないが、マックス・ウエーバが、”労働は救済である” といっても、労働が苦痛を伴うものだけのものであれば、これほどまでに、近代資本主義は伝播しなかったであろうと思われる。
パスカルが、看破したように、人間は ”気晴らし” を求めているが、労働もその要素をあわせ持っていたからこそ、今日の近代資本主義の隆盛を迎えたといえないだろうか。
因みに、今日のヨーロッパにおける経済状況は、プロテスタントが占める割合が比較的多い北欧の経済が順調で、プロテスタントが占める割合が少ない南欧の経済は危機に瀕している。
これは、マックス・ウエーバがいう、プロテスタンティズムの倫理が比較的浸透している北欧諸国とそうでない南欧諸国の差によって生じているかもしれない。
もしそうであれば、欧州の南北の経済格差は一過性のものではないということになる。
EUの経済格差問題は思いのほか根が深い。
2013年7月8日月曜日
中国の影の銀行
中国で影の銀行(シャドーバンキング)が俄にクローズアップされてきた。
影の銀行とは、金融当局の監視外にある投資銀行やヘッジファンドなどであるが、これが地縁・血縁社会の中国では地方の有力者などがスポンサーとなって作った銀行であり、中央銀行の管理外にある、いはば闇の銀行である。
闇の銀行は、理財商品と呼ばれる高利回りの財テク商品を売り捌き、この商品が不良債権化しおきまりの金融危機コースを辿らんとしている。
日本のバブル経済のころ、これに似たシステムがあった。銀行に当局から規制がかかると、銀行は系列のノンバンクを利用した。銀行は、ハイリスク・ハイリターンの商品は、検査・監督の対象とならないノンバンクにまわした。商品が回転しなくなって、結果金融危機をおこした。
最近の事例では、米国のサブプライム商品がある。米国中央銀行であるFRBの監督外にあり、影の銀行である投資銀行とヘッジファンドが売り捌いたサブプライム商品が不良債権化し、表の銀行業務まで破壊したことは記憶に新しい。
日本の場合、金融危機から立ち直るのに長い年月を要した。塗炭の苦しみを味わい20年以上にも亘る酷いデフレになった。
アメリカの場合は、日本の先例を見てか否か、対応が比較的早く回復した。
が、アメリカの場合は影響が大きく、主要な国を道連れにし一時深刻な金融危機に巻き込んだ。
金融制度が整っている日本やアメリカでさえ、このような金融危機を起こした。
昇竜の勢いで経済発展し、これに伴う諸制度が未整備の中国で金融危機が起きないと思うほうが不自然だ。
少しでも中国経済に関心があれば、最近の中国の影の銀行問題は、ついに来るものがきたと思うに違いない。
重要なことは、この中国版 影の銀行システムの行方だ。
まず、日本への影響。この問題がクローズアップされてから、6月20日、中国の銀行間取引基準金利SHIBORが、翌日物で13.4%になり、病み上がりからやっと回復基調にある日本の株式市場は、まるで地雷を踏んだかのような騒ぎとなった。が、当日と翌日一瞬株式市場は暴落したがすぐに平静を取り戻した。アメリカ、欧州には日本ほどの影響はなかった。このことは、中国の経済が世界に与える影響は大きいものの、金融が世界にあたえる影響は、経済とは異なることを図らずも証明した。
が、現実に中国で金融危機が発生すれば、それはそれで大変なことになる。
特に、日本にとってかなりの打撃となるのは間違いない。
影の銀行システムの破綻は、なによりもまず、中国政府にとっては、大きな痛手となるだろう。
闇金融の業務は、党や政府に直接の責任はないものの、この業務は深く庶民の暮らしと直結しているからだ。
これが破綻したら、庶民の怒りは、党や政府に向かうだろう。そうなれば、庶民の生活に直結するだけに、その怒りは、日本に対する歴史問題や尖閣問題の比ではない。
日本に対する中国の若者の怒りは、もともと官製で醸成され洗脳されたものであり、体験からきたものではない。
この怒りに比べれば、金融危機がもたらしかねない生活破綻の怒りは推して知るべし。
闇金融破綻は、庶民にとって死活問題で、暴動が発生したら、これを止めるのも容易ではないだろう。
中国の国防費は近隣諸国と比し多いといはれているが、どういたしまして、2013年度予算で治安維持費は国防費より3.8%も多い約12.7兆円である。
治安維持費が国防費より多いお国柄で、これ以上庶民の怒りをかうのだけはやめなければならない。
中国共産党の七賢人はそう思いあらゆる手立てを打つに違いない。
闇金融を当局の管理に移し、不良債権処理のソフトランディング決着を目指すのか、あるいは、独裁政権らしく荒療治で一気にハードランディング処理するのか、中国政府の対応に注視しこれから目を離せない。
中国状勢は、統計資料だけに頼っては判断を誤る。
発表される中国の統計資料の信頼性には疑問なしとはしないからである。
むしろ、中国各地で発生する暴動のニュースや不動産市場を注視したほうが、より中国を理解できるかもしれない。
影の銀行とは、金融当局の監視外にある投資銀行やヘッジファンドなどであるが、これが地縁・血縁社会の中国では地方の有力者などがスポンサーとなって作った銀行であり、中央銀行の管理外にある、いはば闇の銀行である。
闇の銀行は、理財商品と呼ばれる高利回りの財テク商品を売り捌き、この商品が不良債権化しおきまりの金融危機コースを辿らんとしている。
日本のバブル経済のころ、これに似たシステムがあった。銀行に当局から規制がかかると、銀行は系列のノンバンクを利用した。銀行は、ハイリスク・ハイリターンの商品は、検査・監督の対象とならないノンバンクにまわした。商品が回転しなくなって、結果金融危機をおこした。
最近の事例では、米国のサブプライム商品がある。米国中央銀行であるFRBの監督外にあり、影の銀行である投資銀行とヘッジファンドが売り捌いたサブプライム商品が不良債権化し、表の銀行業務まで破壊したことは記憶に新しい。
日本の場合、金融危機から立ち直るのに長い年月を要した。塗炭の苦しみを味わい20年以上にも亘る酷いデフレになった。
アメリカの場合は、日本の先例を見てか否か、対応が比較的早く回復した。
が、アメリカの場合は影響が大きく、主要な国を道連れにし一時深刻な金融危機に巻き込んだ。
金融制度が整っている日本やアメリカでさえ、このような金融危機を起こした。
昇竜の勢いで経済発展し、これに伴う諸制度が未整備の中国で金融危機が起きないと思うほうが不自然だ。
少しでも中国経済に関心があれば、最近の中国の影の銀行問題は、ついに来るものがきたと思うに違いない。
重要なことは、この中国版 影の銀行システムの行方だ。
まず、日本への影響。この問題がクローズアップされてから、6月20日、中国の銀行間取引基準金利SHIBORが、翌日物で13.4%になり、病み上がりからやっと回復基調にある日本の株式市場は、まるで地雷を踏んだかのような騒ぎとなった。が、当日と翌日一瞬株式市場は暴落したがすぐに平静を取り戻した。アメリカ、欧州には日本ほどの影響はなかった。このことは、中国の経済が世界に与える影響は大きいものの、金融が世界にあたえる影響は、経済とは異なることを図らずも証明した。
が、現実に中国で金融危機が発生すれば、それはそれで大変なことになる。
特に、日本にとってかなりの打撃となるのは間違いない。
影の銀行システムの破綻は、なによりもまず、中国政府にとっては、大きな痛手となるだろう。
闇金融の業務は、党や政府に直接の責任はないものの、この業務は深く庶民の暮らしと直結しているからだ。
これが破綻したら、庶民の怒りは、党や政府に向かうだろう。そうなれば、庶民の生活に直結するだけに、その怒りは、日本に対する歴史問題や尖閣問題の比ではない。
日本に対する中国の若者の怒りは、もともと官製で醸成され洗脳されたものであり、体験からきたものではない。
この怒りに比べれば、金融危機がもたらしかねない生活破綻の怒りは推して知るべし。
闇金融破綻は、庶民にとって死活問題で、暴動が発生したら、これを止めるのも容易ではないだろう。
中国の国防費は近隣諸国と比し多いといはれているが、どういたしまして、2013年度予算で治安維持費は国防費より3.8%も多い約12.7兆円である。
治安維持費が国防費より多いお国柄で、これ以上庶民の怒りをかうのだけはやめなければならない。
中国共産党の七賢人はそう思いあらゆる手立てを打つに違いない。
闇金融を当局の管理に移し、不良債権処理のソフトランディング決着を目指すのか、あるいは、独裁政権らしく荒療治で一気にハードランディング処理するのか、中国政府の対応に注視しこれから目を離せない。
中国状勢は、統計資料だけに頼っては判断を誤る。
発表される中国の統計資料の信頼性には疑問なしとはしないからである。
むしろ、中国各地で発生する暴動のニュースや不動産市場を注視したほうが、より中国を理解できるかもしれない。
2013年7月1日月曜日
消費税増税
政府は、今4~6月の経済状況をみて10月ごろ消費税増税の可否を判断をするというが、なぜか消費税増税の既成事実化が着々と進んでいるようにみえる。
消費税増税による景気冷え込みを防ぐため、住宅購入者に対する補助金支給が検討されたり、新聞では消費税の軽減税率適用の要望が一段とヒートアップしている。
このままだと、政府が増税可否の判断するという10月には、増税が既成事実化され、景気の如何に拘わらず、実務的に増税を中止するという選択肢は実質上排除されているかもしれない。
わが国における消費税増税による税収の落ち込みは平成9年の橋本内閣で経験済みである。
ようやく上りかけた税収に水をさし腰折れさせた。(下図)
一般会計税収の推移
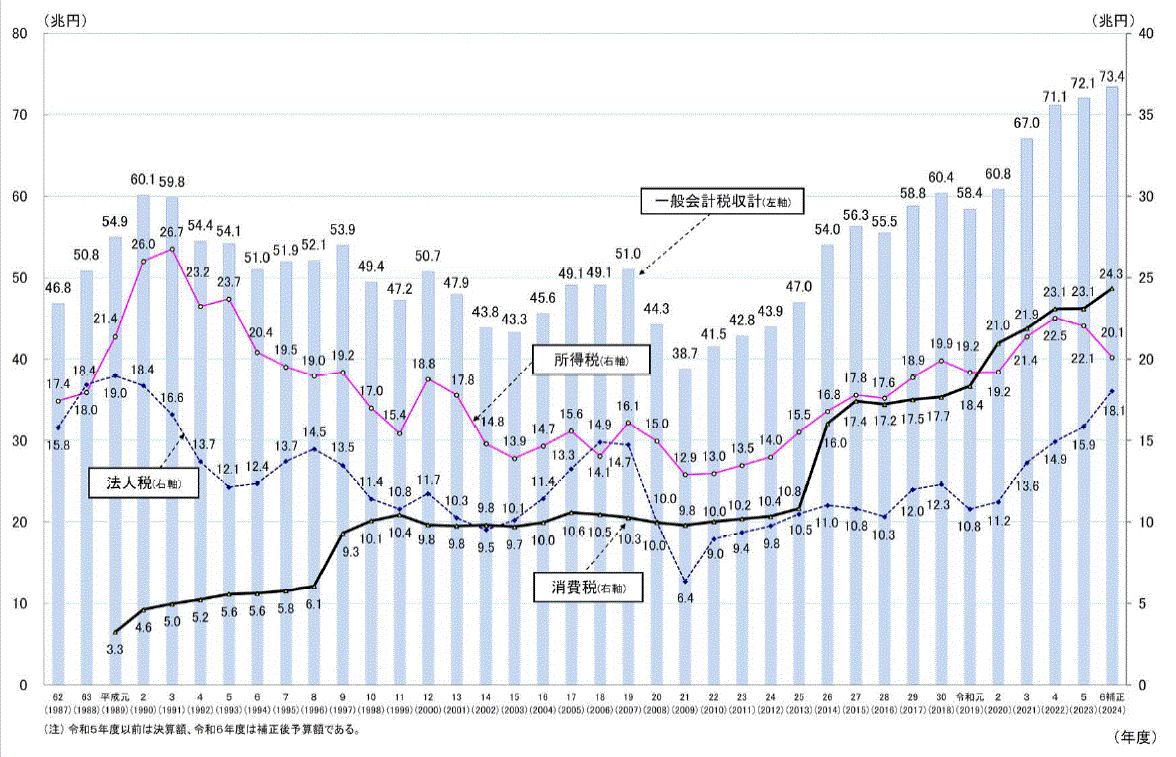
平成元年4月1日 消費税新設(3%)
平成 9年4月1日 消費税増税(3%→5%)
(注)23年度以前は決算額、24年度は補正後予算額、25年度は予算額である。
財務省統計資料から
英国の事例でも同じことがいえる。2011年1月増税実施後景気が低迷している。(下図)
なお悪いことに英国の場合は米国のFRB以上にものすごい勢いで金融緩和しているにも拘わらず景気低迷を阻止できないでいる。
わが国は、アベノミクスでようやく景気回復の端緒についたばかりである。
ここで消費税増税を実施すれば、英国の二の舞になりかねない。
大胆な金融緩和も、増税にたいしては景気の腰折れを防ぐことはできない。
上記二つの事例からみても、来年4月からの消費税増税には無理がある。
が、この無理を押し通そうとする強力な勢力がある。財務省である。財務省は組織をあげて消費税増税に邁進している。
増税は、財務省の歳出権を増大させ裁量権を増大させる。柴田弘文 立命館大学名誉教授が指摘しているように、財務省は税収予測値を操作することにより省益最大化を目指しているが、消費税増税も例外とは思えない。
省益最大化は財務省の最優先課題であり、そこには国益は存在しない。
なぜこのようになったのか、その原因を探るには戦前に遡って俯瞰する必要がある。
欧米と異なり、わが国には貴族階級は存在しなかった。が、明治政府は貴族階級に換わるものを教育制度に求めた。日本版 ”科挙” の導入である。
一高・東大法学部をもって日本の指導者階級の養成機関と位置付けた。
国民もこれに呼応し、貧しくとも一高を目指せる能力を見込まれた若者は郷土をあげて支援した。
かかる支援は大変な美談とされた。
これら、佐藤紅緑描く ”ああ玉杯に花うけて” 世代の若者は一高・東大法学部を卒業すれば官僚中の官僚、大蔵省に入省し、自然と勇者の責任 (noblesse oblige)を身につけた。省益などかまわず、国のためにやってやろう、という気概にあふれていた。
ところが、戦後の教育は、自我を全面にだす教育が善とされ、 共同体意識、連帯意識が薄れた。受験戦争が勃発し受験生はこれに勝利することのみに集中した。
結果は、誰のお陰でもない、自分の力のみで獲得したものであるから、自分の利益を最優先するといってはばからない若者を誕生させた。
これがひいては国益などかまわない省益最優先官僚の誕生となった。
発展途上にあったわが国の戦前の教育制度はそれなりに有効に働いた。
が、戦後の教育制度のもと勇者の責任を放棄した官僚が、戦前の特権だけを受け継いだ。
これが最大の矛盾点であり、腐敗・腐蝕の原因となった。
義務と責任を伴わないで、特権だけ受け継いだ官僚が、どのような行動様式をとるか。
待ち受けているのは、果てしない腐敗と腐蝕である。
官僚を監視する制度・体制が今ほど望まれることはない。これは直ちに望むべくして得られるものでもないかもしれない。
が、望み求め続けること、それ自体が官僚の監視機能ともなりうる。
消費税増税の行方は、政治家、官僚および国民の行動様式を占ううえで貴重な試金石となる。
消費税増税による景気冷え込みを防ぐため、住宅購入者に対する補助金支給が検討されたり、新聞では消費税の軽減税率適用の要望が一段とヒートアップしている。
このままだと、政府が増税可否の判断するという10月には、増税が既成事実化され、景気の如何に拘わらず、実務的に増税を中止するという選択肢は実質上排除されているかもしれない。
わが国における消費税増税による税収の落ち込みは平成9年の橋本内閣で経験済みである。
ようやく上りかけた税収に水をさし腰折れさせた。(下図)
一般会計税収の推移
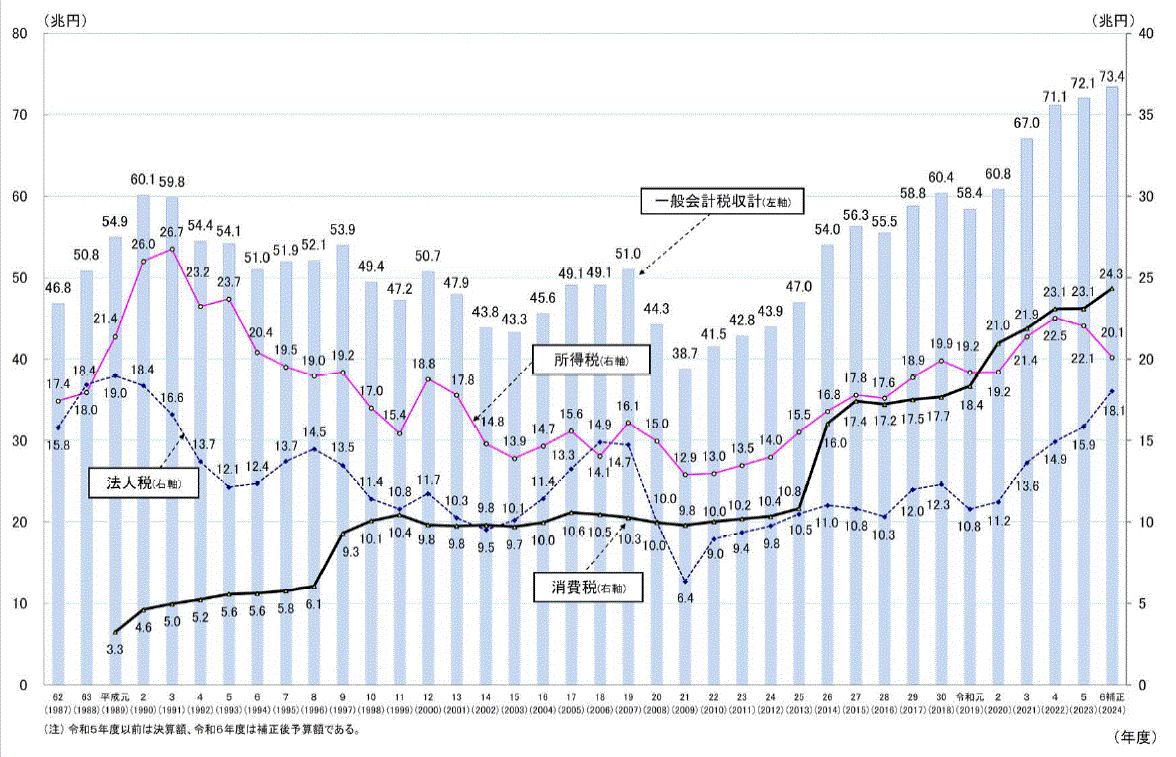
平成元年4月1日 消費税新設(3%)
平成 9年4月1日 消費税増税(3%→5%)
(注)23年度以前は決算額、24年度は補正後予算額、25年度は予算額である。
財務省統計資料から
英国の事例でも同じことがいえる。2011年1月増税実施後景気が低迷している。(下図)
なお悪いことに英国の場合は米国のFRB以上にものすごい勢いで金融緩和しているにも拘わらず景気低迷を阻止できないでいる。
産経新聞特別記者 田村秀男氏作成資料から
わが国は、アベノミクスでようやく景気回復の端緒についたばかりである。
ここで消費税増税を実施すれば、英国の二の舞になりかねない。
大胆な金融緩和も、増税にたいしては景気の腰折れを防ぐことはできない。
上記二つの事例からみても、来年4月からの消費税増税には無理がある。
が、この無理を押し通そうとする強力な勢力がある。財務省である。財務省は組織をあげて消費税増税に邁進している。
増税は、財務省の歳出権を増大させ裁量権を増大させる。柴田弘文 立命館大学名誉教授が指摘しているように、財務省は税収予測値を操作することにより省益最大化を目指しているが、消費税増税も例外とは思えない。
省益最大化は財務省の最優先課題であり、そこには国益は存在しない。
なぜこのようになったのか、その原因を探るには戦前に遡って俯瞰する必要がある。
欧米と異なり、わが国には貴族階級は存在しなかった。が、明治政府は貴族階級に換わるものを教育制度に求めた。日本版 ”科挙” の導入である。
一高・東大法学部をもって日本の指導者階級の養成機関と位置付けた。
国民もこれに呼応し、貧しくとも一高を目指せる能力を見込まれた若者は郷土をあげて支援した。
かかる支援は大変な美談とされた。
これら、佐藤紅緑描く ”ああ玉杯に花うけて” 世代の若者は一高・東大法学部を卒業すれば官僚中の官僚、大蔵省に入省し、自然と勇者の責任 (noblesse oblige)を身につけた。省益などかまわず、国のためにやってやろう、という気概にあふれていた。
ところが、戦後の教育は、自我を全面にだす教育が善とされ、 共同体意識、連帯意識が薄れた。受験戦争が勃発し受験生はこれに勝利することのみに集中した。
結果は、誰のお陰でもない、自分の力のみで獲得したものであるから、自分の利益を最優先するといってはばからない若者を誕生させた。
これがひいては国益などかまわない省益最優先官僚の誕生となった。
発展途上にあったわが国の戦前の教育制度はそれなりに有効に働いた。
が、戦後の教育制度のもと勇者の責任を放棄した官僚が、戦前の特権だけを受け継いだ。
これが最大の矛盾点であり、腐敗・腐蝕の原因となった。
義務と責任を伴わないで、特権だけ受け継いだ官僚が、どのような行動様式をとるか。
待ち受けているのは、果てしない腐敗と腐蝕である。
官僚を監視する制度・体制が今ほど望まれることはない。これは直ちに望むべくして得られるものでもないかもしれない。
が、望み求め続けること、それ自体が官僚の監視機能ともなりうる。
消費税増税の行方は、政治家、官僚および国民の行動様式を占ううえで貴重な試金石となる。
登録:
投稿 (Atom)
