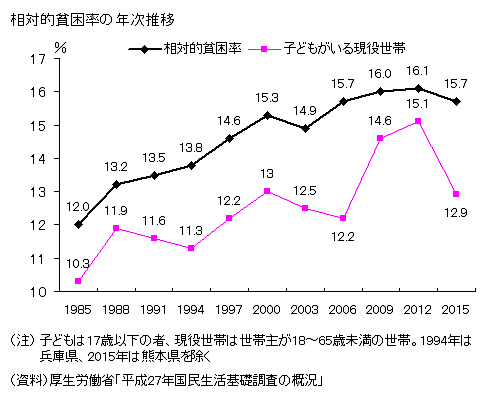現代でも、どこかの政治家あるいは野心家がオフレコで発言してもおかしくない。
世の中が平時ならざる時にはかかる思想家の論文は研究に値する。
「ある国を奪いとるとき、征服者はとうぜんやるべき加害行為を決然としてやることで、しかもそのすべてを一気呵成におこない、日々それを蒸し返さないことだ。さらに、蒸し返さないことで人心を安らかにし、恩義を施して民心を摑まなくてはいけない。
とにかく臆病風に吹かれたり、誤った助言に従ったりして、逆のことをやってしまうと、その人は必然的に、いつも手から短剣が放せなくなる。
臣下にしても、新たな危害が間断なくやってくるから、君主に安心感がもてなくなり、君主もそうした臣下を信じるわけにいかなくなる。
要するに、加害行為は一気にやってしまわなくてはいけない。そうすることで、人にそれほど苦汁をなめさせなければ、それだけ人の憾みを買わずにすむ。
これに引きかえ、恩恵は、よりよく人に味わってもらうように、小出しにやらなくてはいけない。」
(マキャヴェリ著 池田廉訳 君主論)
また現代のわれわれが思わず眉をひそめてしまうようなフレーズもある。
「そもそも人間は、恩知らずで、むら気で、猫かぶりの偽善者で、身の危険をふりはらおうとし、欲得には目がないものだと。(中略)
たほう、人間は、恐れている人より、愛情をかけてくれる人を、容赦なく傷つけるものである。
その理由は、人間はもともと邪まなものであるから、ただ恩義の絆で結ばれた愛情などは、自分の利害がからむ機会がやってくれば、たちまち断ち切ってしまう。
ところが、恐れている人については、処刑の恐怖がつきまとうから、あなたは見離されることがない。ともかく、君主は、たとえ愛されなくてもいいが、人から恨みを受けることなく、しかも恐れられる存在でなければならない。」
(同上)
マキャベリは、道徳とか宗教など一切無関係に、純粋に君主が如何にして国を統治すべきか,リーダーの条件とはなにかを論じた。
また人間関係について、上司と部下、移り気な大衆などについて細部にわたり自論を展開した。
恰もシェークスピアのジュリアス・シーザーとかリチャード三世などの劇を論文にしたかのように。
君主論は、メディチ家に職を得ようとして書かれたとも言われ、具体的、実用的に書かれている。
単なる儀礼的な献上書に止まらず、説得力があるのはそのためであろうか。
現実の彼は、外交官として華々しく成功したと言うわけではなかった。
否、むしろ運も味方せず失敗のほうが多かったようだ。
それがかえって彼を著述に向かわせたのかもしれない。
彼は、身近に見た君主たちを通じて、道徳とか宗教とかにとらわれることなく、統治とか政治権力について自ら見聞した事柄に基づき率直に自論を展開した。
16世紀初頭という時代背景から彼の考えはとうてい受け入れらるるようなものではなかった。
マキャヴェリ没後、君主論が時をおかずして出版されるとすぐにカトリックの聖職者が非難の声をあげ、1559年ローマ教皇庁は君主論を禁書目録に入れた。
今日われわれが、いわゆる”マキャヴェリズム”についての冷酷非道という一般的な印象はこの事件が発端でいまだにその印象を引きずっているのかもしれない。
マキャヴェリとは、一体どのような人物であったのか、君主論の背景とあわせ、彼の素顔にせまりたい。