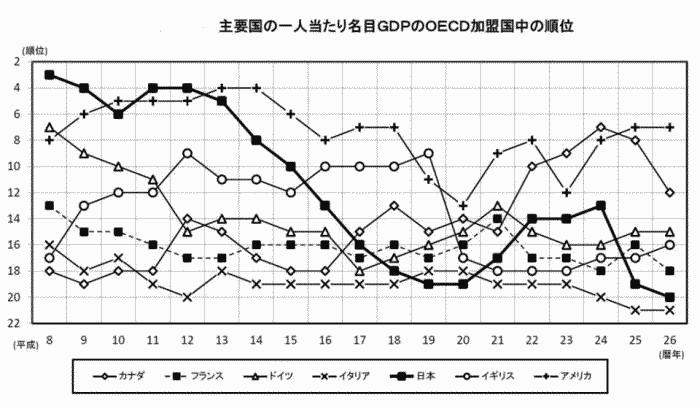さらに2010年に民主党管直人政権が閣議決定した2020年までに基礎的財政収支(プライマリー・バランス)を黒字化する目標が未だ生きていて取り消されていない。
デフレ脱却のためこの目標を撤回すべしと主張する人が政府関係者にもいる。藤井聡内閣官房参与は自著『プライマリー・バランス亡国論』でアルゼンチンやギリシャを例に、プライマリー・バランス改善に向けて歳出削減や増税に踏み切れば、景気が冷え税収が減り、結果として財政が悪化すると警告している。
一方政策当局は、財政健全化のためには増税やプライマリ-・バランス黒字化目標は必須であると主張する。
だがわれわれは学者や政策当局の議論を俟つまでもなくデフレ時の緊縮財政は財政政策の禁忌であることを昭和恐慌の教訓から得ている。
にもかかわらずなぜこれが生かされないのか。これが小論の核心テーマである。
まず、わが国の金融や財政政策についてそれぞれの責任者はどう考えているのだろうか。
麻生財務大臣は、当局の責任者として財政健全化は喫緊の課題であるという。ところが大臣就任以前の発言はこれと真逆である。 日本に債務問題はない。日本の国債は円建てでその90%以上を日本国民が買っているから。このような主旨を講演会などで発言している。
黒田日銀総裁も総裁就任以前これと同じ類のことを文書で発信している。財務官時代の2002年4月30日アメリカ格付け会社による日本国債格下げに対し反論して曰く。
・ 自国通貨建て国債のデフォルトは考えられない。
・ マクロ的に見れば、日本は世界最大の貯蓄超過国
ここは社会科学の出番である。これによってはじめてこの問題が明らかになるであろう。
・ その結果、国債はほとんど国内で極めて低金利で安定的に消化されている
・ 日本は世界最大の経常黒字国、債権国であり外貨準備も世界最高
このように政策当局の責任者は日本に財政の問題は無いと現在の主張と真逆の発言をしている。
現在わが国の論調は、「債務が拡大し財政破綻のおそれがあり財政健全化は喫緊の課題である」との主張が大勢をしめる。
上記政策責任者がそれを率先推進しているのもその原因の一つであろう。
一方、彼らは本音として長引くデフレを脱却するには財政健全化などではなく緊縮財政を止め大胆な財政政策で景気を刺激しなければならない。2%の物価目標を達成するためにも金融だけでなく財政の支援が必要であると考えているに違いない。
彼らにしてみれば、こんなことは経済学者やエコノミストに言われるまでもなく100も承知200も合点のことだろう。 それが証左に財務大臣や日銀総裁に就任する前に自説を得意げに開陳しているではないか。わかっちゃいるけどそうしない、あるいはそうできない。
なぜこういうことになるのか。繰り返し言おう。これが本問題の核心である。
・ 日本は世界最大の経常黒字国、債権国であり外貨準備も世界最高
このように政策当局の責任者は日本に財政の問題は無いと現在の主張と真逆の発言をしている。
現在わが国の論調は、「債務が拡大し財政破綻のおそれがあり財政健全化は喫緊の課題である」との主張が大勢をしめる。
上記政策責任者がそれを率先推進しているのもその原因の一つであろう。
一方、彼らは本音として長引くデフレを脱却するには財政健全化などではなく緊縮財政を止め大胆な財政政策で景気を刺激しなければならない。2%の物価目標を達成するためにも金融だけでなく財政の支援が必要であると考えているに違いない。
彼らにしてみれば、こんなことは経済学者やエコノミストに言われるまでもなく100も承知200も合点のことだろう。 それが証左に財務大臣や日銀総裁に就任する前に自説を得意げに開陳しているではないか。わかっちゃいるけどそうしない、あるいはそうできない。
なぜこういうことになるのか。繰り返し言おう。これが本問題の核心である。
日本は今も昔も、そして良くも悪くも官僚国家である。また空気が支配する社会でもある。
ここにこの問題解決の糸口がある。これらを解明し課題のまとめとしよう。