「六〇年代は経済的に見て、これ以上いい時代はなかったといえるほど好景気に恵まれた時代であった。(中略)
経済は国民全員に仕事を与えることができるかのように見えた。仕事があり余るほどあっただけでなく、その賃金もこれまで以上に高く、毎年上昇していた。低賃金労働者にとってもこれほどいい時代はなかったろう。」
(早川書房ポール・クルーグマン著格差はつくられた 三上義一訳)
戦後の六〇年代はアメリカでは経済格差が問題になることはなかった。アメリカ国民はほとんどが一様に豊かさを分け合っていた。
日本も高度経済成長期には国民の間に格差の意識はなかった。この点でアメリカと軌を一にしている。最近我が国では、新興の目覚しく成功した経営者を、恰も芸能人かスポーツ選手のごとくビジネス雑誌などでとりあげ時代のヒーロ扱いすることなども、これまたアメリカ社会に似かよっている。
成功した経営者は言う。
「金持ちになるのに何が悪い。自分の才覚と努力で勝ち得たものだ。何もとやかく言われる筋合いはない。格差が問題だなどと、とやかくいうおまえこそ引かれものの小唄ではないか」 と。
あるいはそうかもしれないが、これに疑問を呈する人がいることもまた事実だ。それも権威ある人が。
アメリカのノーベル経済学者ジョセフ・スティグリッツ教授である。
彼は、富裕層は民間企業が政府と結びつき公共サービスの仕組みを変え、市場のルールを自分に有利に働くように変え富を築いていると主張している。
経営者の才覚と努力によってのみで生み出された富ではないといっている。
安倍政権の成長戦略の産業競争力会議で審議されている内容を見ると、なかにはスティグリッツ教授の指摘そのものに該当するものがある。
歴史的にいえば、日本はもともと経済格差が大きい国であった。戦前のある時期までは人口の1%が課税所得の20%を占めていたというデータがある。この1%とは資本家と地主である。
第2次大戦後、財閥解体、農地改革、インフレおよび富裕層に対する所得税と相続税の引き上げなどにより経済格差が急速に縮小し、高度経済成長期には一億総中流といわれたぐらい経済格差が縮小した。
が、バブル崩壊後のここ20年の間に再び格差が拡大している。
前述のような新興の目覚しく成功した経営者が増加したことは確かだが、アメリカに比べればまだまだつましいものだ。
アメリカの経済格差は、戦前の日本のように、1%の富裕層が国民の富の20%を所有することにある。
我が国の経済格差とは、富裕層がより豊かになったからではなく、貧困層が急速に増えたからである。
そのことは、経済格差を反映するといわれる、全国民の年収の中央値の半分に満たない国民の割合をさす相対的貧困率の推移に表れている。(下図)
急速にすすむ高齢化、いつまでも脱却できないデフレ・成長鈍化、非正規労働者の急増 これらがいやおうなく貧困層を急増させ、結果的に国民の間に不平等感をもたらしている。
単一民族、単一言語社会の我が国では、国民の間の絆は、多少の経済格差などでは揺るがない。
が、そういうことがいえるのは平時だからこそ。
鬱積した不満・不平等感は深く潜行し、行き場を失うときが、いつかかならずおとずれる。
経済格差を助長するような政策は論外だが、これを放置するのも、それに劣らず不作為の罪であろう。
とてつもない外圧があったとき、これに抗し得るのは、国民の間の信頼と結束である。
いかにその他の条件が充たされようと、これなくして外圧に抗し得ないことを歴史が証明している。
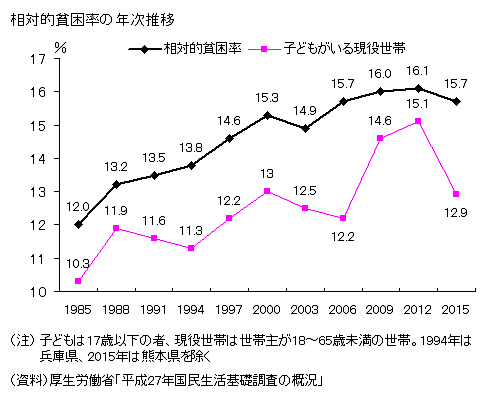
0 件のコメント:
コメントを投稿